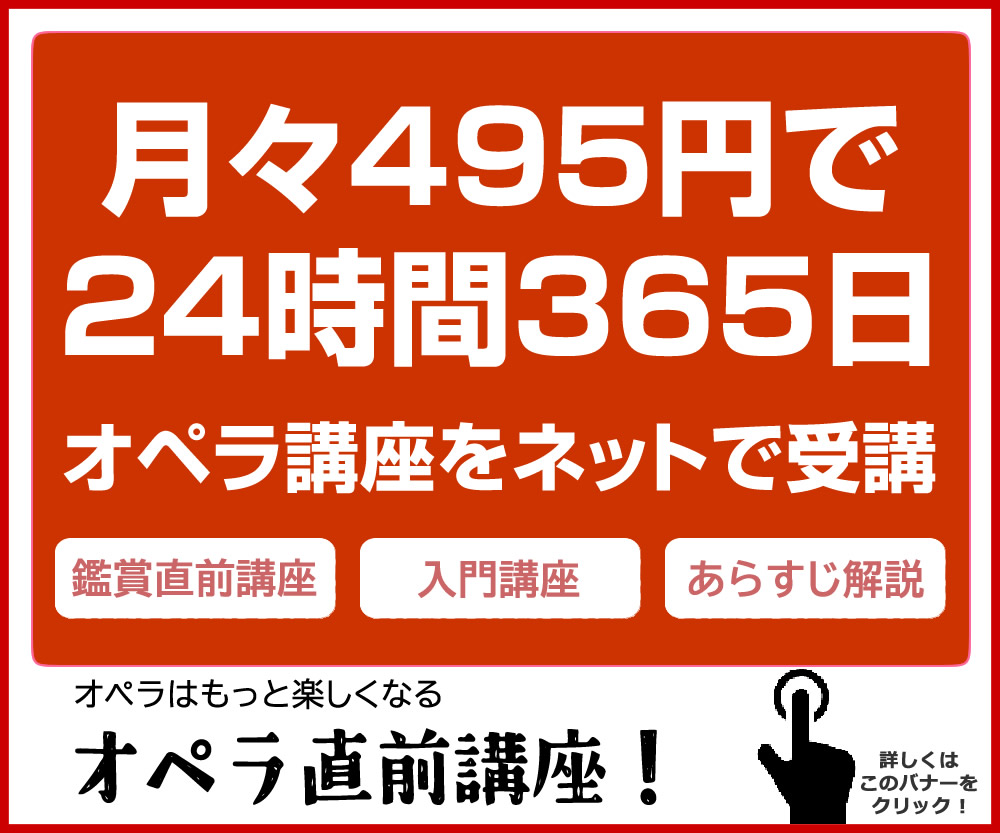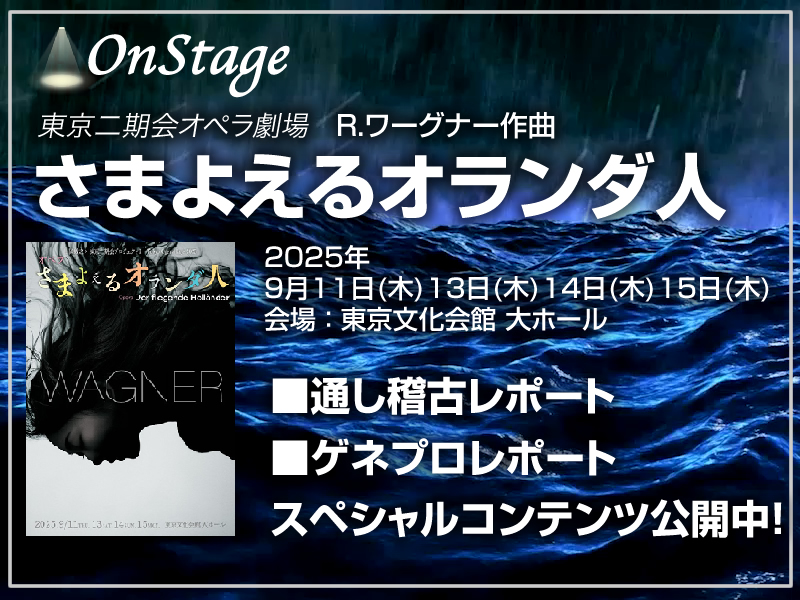ロベルト・アラーニャ インタビュー(2024年3月29日)


Zoomインタビューにて









ロベルト・アラーニャ インタビュー
ロベルト・アラーニャが18年ぶりに来日を果たします。
来日に先立ち、リモートインタビューが実施されましたので、その模様を掲載いたします。
彼の素顔が表れております。
思い起こせば、ロベルト・アラーニャという歌手は、オペラの商業化時代に翻弄されたアーティストなのではないだろうか。
世に出てから、その才能は開花するが、1990年にビックバンを起こした『3大テノール』は、既にピークを過ぎており、その大成功コンセプトは、オペラのビジネス二番煎じの二匹目のどぜうを狙う興行主により、すぐさま『ポスト3大テノールを探せ!』候補に上がり、周囲からもてはやされる、そうなると、自制をしていても、自身も若気の至りとなるのは当然だ。
同世代で言いうとホセ・クーラ、マルッセロ・アルバレス、ジュゼッペ・サッバティーニなど、名が上がる。しかし、時代は、ネットバブル崩壊時代に突入しており、一人で、ベルカント~プッチーニ~ワーグナーまで歌う(歌ってしまう)様な歌手は、求められておらず、1億総評論家時代になってきている時代で、過去に読んだことのある二番煎じの使い古された言葉の羅列の自称評論家が乱立することとなる。
その中で、ロベルト・アラーニャの来日リサイタルでも、元ワイフのアンジェラ・ゲオルギューとのDuoコンサートでは、1曲歌っては、二人でチュッチュ!し、我々は大枚をはたいて一体、何を見せられているのだろう?と自問自答したものだった。当然、ネットでもざわつく。果てには、ミラノ・スカラ座《アイーダ》の冒頭アリアでのブーイングで、自ら闘将ラダメスを降板してしまう。其の後、スカラ座前広場で歌ったり、話題に事欠かない辺り、やはり、『スターは、持っている!』のであろう。
しかし、彼には実力があったことは周知の事実であった。だからこそ、『彼の今』が気になって仕方なかった。キャストに彼の名が上がると、聞きたくなる、それも、ワクワクしながら聞くのではなく、『今のアラーニャはどうなの?』という、ちょっと冷めた気分で客席に座ったものだった。結果、『大丈夫じゃん!』って言うか、『なかなかいいじゃん!』という感想にたどり着く。なんとも、『不思議なスターテノールだ』そのアラーニャが、還暦を過ぎ、18年ぶりに来日し、コンセプトもターゲットを『プッチーニ』に絞ってのプログラム構成だ。『アラーニャの今』が知りたくて、インタビューで、少し意地悪な質問をした。『あなたは、もう、ベテランですが、今の声は、ピークなのか、黄昏期なのか、まだ、変化(成長)を楽しんでいいのか?』と。。。彼は、真摯に、プライベートな事まで、赤裸々に答えてくれた。インタビュー内容は、下記。
私も、前列席を購入済み! 6/9『アラーニャの今』を見届けよう。
文:坂田康太郎
ロベルト・アラーニャ リサイタル
THE GREAT PUCCINI ~プッチーニ没後100周年 スペシャル・プログラム~
日時:2024年6月9日
場所:サントリーホール 大ホール
https://ticket.rakuten.co.jp/music/classic/rtcq24b/
| (質問)アラーニャさんといえばテノールのほとんどのレパートリーを制覇しています。例えば、プッチーニとヴェルディを例にとってみても、声質の他にも、まったく筋肉の使い方が違うといわれますが、アラーニャさんは このような音楽的要素以外の違いや難かしさをどのように克服しているのでしょうか。 |
|---|
| (回答)テクニックは同じだと言えます。やはり自分の声で歌わなければなりませんので、声を無理やり大きくするというものではありません。自分の音で歌うということなのです。 ただ、確かにプッチーニは声のボリュームが必要になってきます。それは、オーケストラが強い音を出しているので、声のメロディーはそれを超えなければならないということです。 それを超えるにはどうすれば良いかと言うと、より幅広い音を出すことなのですが、それには結局のところ「ベルカント」の唱法が必要となってきます。 「ベルカントの歌」は何かと言うと、それは純粋な音で、かつ軽やかで明るさを持って、ただそれを響かせる必要があると言うことです。プッチーニとヴェルディでは、また異なる部分があり、ヴェルディにはより陰鬱な、悲しい音色が必要になってきます。音は丸みのある音で、ディクションは非常にはっきりとしなければならないという特徴がヴェルディにはあります。しかし、ヴェルディにとってもベースとなる部分は同じであると、私は考えています。 |
| (質問)あらゆるレパートリーをこなすアラーニャさんですが、6月の来日公演は周年を記念したオール・プッチーニ・プログラムとなっています。アラーニャさんが考えるプッチーニの音楽の美しさ、作品の魅力、そして歌うことの難しさはどんなところですか? |
|---|
| (回答)プッチーニは天才的であると思います。世界で最も有名な、最も上演されるオペラを5つ選ぶとすると、その中の3つがプッチーニなのではないかと思います。例えば、「カルメン」、「ドン・ジョヴァンニ」「蝶々夫人」「トスカ」「ラ・ボエーム」というところではないでしょうか。もちろん「リゴレット」なども入ってきますが。 けれどもプッチーニは、最初のいくつかの中に確実に入っているものです。それはなぜかと言うと、プッチーニは非常にモダンであり、映画的な音楽であり、とても感情を表す音楽であるため、直接聴衆の心に触れるのです。それは自然な人間性を表現しています。 例えば、“神“という宗教的なものであったり、神話であったり、もしくは歴史的な人物などが登場するという物語ではなく、非常に素朴なごく普通の人々のお話です。例にとれば、「ラ・ボエーム」もそうですし、「外套」や「マノン・レスコー」もそうです。だから彼の音楽は一般の人々の心に触れるのだと思います。 |
| (質問)今回のプログラムは「誰も寝てはならぬ」や「星は光りぬ」等の名アリアはもちろん、プッチーニの初期作品である「妖精ヴィッリ」や「エドガール」が含まれており、これらは初期作品にもかかわらず、ドラマティックな美しいアリアが多いです。しかし、あまり上演される機会が多くありません。なぜプログラムに入れてみようと思われたのでしょうか? |
|---|
| (回答)今年はプッチーニ没後100年の記念の年なので、プッチーニに捧げるコンサートにしようと思いました。私はすでにピアノ伴奏でプッチーニに捧げるコンサートを最近グシュタードで行いましたが、オーケストラとのコンサートは日本で行うものが初めてとなります。 その後パリでも同じ内容の公演を行い、スカラ座でもまたピアノとコンサートをする予定です。私のキャリアではずっとプッチーニに伴われたコンサートを行ってきました。 40年間のキャリアの中でプッチーニを歌わなかった年はないと思います。ですから私にとってプッチーニというのは、非常に重要な作曲家です。ひとりのテノールが、彼が書いたあらゆるタイプの感情を表現する様々なオペラ・アリアを歌うことはとても興味深いと思うのです。今回のプログラムで私は、時系列的に最初に書かれたものから順に歌っていく予定です。まず、最初に書かれた作品「妖精ヴィッリ」。これは内容的にとても濃いもので、歌うのも難しい作品です。そのあとに「エドガール」。これもとてもドラマティックな作品です。この最初の二つの作品にはすでにプッチーニの才能が現れています。 その後、彼の天才的な才能が現れた最初の有名な作品となるのが「マノン・レスコー」。この「マノン・レスコー」からは3つのアリアを歌う予定です。それに続けて「蝶々夫人」や「西部の娘」という作品を歌っていく予定ですが、今回はプッチーニのテノールのアリアがある作品を1日で歌うという内容になっています。彼のオペラの中で一曲、テノールのアリアの無い曲がありますが、それは「修道女アンジェリカ」。女声だけのオペラなのでテノールは出演しませんね(笑)。 |
| (質問)先程「プッチーニ作品は人間的である」というお話がありましたが、プッチーニ作品では役者としての側面も問われます。最も役者として強い要素があると思われる役柄やアリアはありますか? またどの役柄が今のご自身に一番近い、あるいは、ご自身の理想の姿でしょうか? |
|---|
| (回答)プッチーニは私がずっと愛してきた作曲家です。なぜなら、非常に偉大な作曲家であるからです。若い頃はやはり、「ラ・ボエーム」のロドルフォに自分を投影していた部分がありますね。それは私が彼に少し似た人生を歩んできたというか…私の最初の妻がなくなったのは、私が29歳のときに病気になり、亡くなったのは私が30歳のときでした。その頃はボヘミアン的な生活をしていて、希望や歌う喜びはあるけれども、お金がなくて。それでも一緒にいるということを大事にしていました。そういった倹しい暮らしをしていたので。そのような部分でロドルフォに自己投影していた部分があります。 その後は「つばめ」のような作品ですね。ちなみに「つばめ」はプッチーニ作品において、あまり重要とは考慮されてないことが多い作品ですが、私は決してそうではない、偉大な作品だと考えています。その「つばめ」の主人公に自己投影したり。 その後はもっと成熟したテノールの役に挑戦してきました。なので、今回歌うことの挑戦は、若い時に適している作品、たとえば「ラ・ボエーム」や「ジャンニ・スキッキ」のような作品、もしくは「マノン・レスコー」のような作品(「マノン・レスコー」はドラマティックな面もありますが)から始まって、「トスカ」や「トゥーランドット」や「西部の娘」などの作品を一緒に歌い、「蝶々夫人」のような作品も歌うというところにあります。 ちなみに「蝶々夫人」のピンカートンは、とても態度が粗野な男ではありますけれども、私は彼のことを“裁く”という気持ちを持ったことはありません。なぜなら、仮に私が同じシチュエーションにあったら、どういうことをするのかは、実際にそうなってみないと分からないですからね。登場人物を歌うときは、それを自分は同一視して、その人物になりきろうとします。そういうことも含めて、誰にでも起こり得ることだと思って、役に入っています。 |
| (質問)「自分のキャリアの中でプッチーニを歌わなかった年はなかった」というお話がありましたが、今までで一番印象に残っているプッチーニ作品の舞台を教えて頂けますか? |
|---|
| (回答)本当にたくさんあって、全てだと言いたいくらいですが、ひとつ今思い浮かんだのは、メトロポリタン歌劇場で歌った「マノン・レスコー」でしょうか。これは私が「道化師」を歌っていた時に、代役として、とても急いで呼ばれて引き受けた作品だったので、自分にとってとてもリスクがあり、とても大きな挑戦となった決して忘れられない舞台になりました。 もちろんそれが上手くいったから、ということもあるのですが、私はその初日に合わせて、ものすごい時間を集中して勉強しました。この作品を私が勉強し始めたとき、既に舞台稽古が始まっていたのです!8日間で役をものにして舞台で歌いました。そういう思い出があるのが、このメトロポリタン歌劇場で歌った「マノン・レスコー」です。 |
| (質問)アラーニャさんの経歴やご活動について伺いたいと思います。アラーニャさんは近年、宗教曲から、知られざるフランスオペラ、そして新しいオペラ作品なども初演されるなど、多方面でご活躍されていますが、アラーニャさんが音楽家としてさらに描いている将来像を教えてください。 |
|---|
| (回答)私は“音楽”にとても情熱を持っています。オペラ歌手になる前、子供の頃から文学や音楽が大好きで、歌うことが大好きでした。それは私のファミリーに、そういった人々がたくさんいたからです。例えば、私の曾お爺さんは、アメリカに渡って歌手をしていました。そういった経歴のある人もいましたし、音楽がすごく大好きでした。ですから、いろんな役に挑戦する、それからオペラ以外の色々なことに挑戦するというのも、自分のそういったバックグラウンドから来ています。ポップスも好きですし、伝統音楽も好きですし。自分が感情をゆさぶられて、感動を人に届けられるということが大事です。オペラファン以外の広い音楽ファンの人たちに届くものを歌いたいといつも思っています。だから、どういった作品でも興味を持ちますし、これからも広く好奇心を持って活動していきたいと思っています。何をするにも、自分自身の全てを人に捧げたいし、これからも誠実にキャリアを歩んでいきたいと思っています。 |
| (質問)日本には1990年に「椿姫」で初来日され、2006年のボローニャ歌劇場「イル・トロヴァトーレ」まで何回か来日されました。アラーニャさんのキャリアにとって日本はどんな存在でしたか?また日本で特に心に残っている思い出の公演などがあればお聞かせください。 |
|---|
| (回答)日本はすごく好きな国です。最初の「椿姫」で来日した際に日本の音楽家の皆さんのプロフェッショナルな姿勢に心打たれました。日本という国もすごく感じが良く、皆さんが歓迎して下さったことも、とても嬉しかったです。それから何度も訪れて、オペラだけでなくリサイタルなども開きましたが、日本のコンサートホールは音響が素晴らしく、お客様がいつも暖かく迎えてくれたことが私はとても嬉しかったです。 それだけではなく、私は自分の家族にも日本に来て欲しいと感じて、父親にも同行してもらって「やはり日本はいいね」と家族で楽しく来日した思い出があります。 若い頃は、自分がアーティストとして有名になる必要があったので、日本にごく若い頃に呼ばれたという事実は、私に世界でキャリアを築いていくための自信や勇気を与えてくれました。日本でそのようなオペラの重要な役を頂いて、つまり自分を信じてくれた劇場で歌う機会を与え、歓迎してくれたことが私自身に自信を与えてくれていたのです。 |
| (質問)アラーニャさんはテノールとしてとても長いキャリアをお持ちです。しかも第一線で活躍され続けています。その秘訣を教えていただけますか? |
|---|
| (回答)勉強ですね!勉強と仕事を続けること。あと健康もとても大事です。もちろんキャリアの中で、何度も難しい時期はありました。でも、そういう時期も自分がより良くなるための糧になります。どうしてもキャリアの中では良い時期と悪い時期があるのですが、それをどうやって自分を良くする方に役立てるのかということが大事だと思います。 だから秘訣は何と言われれば、それは勉強することと情熱を持つことと答えられるかと思います。特に私がこの仕事を始めた時に、自分の魂の中に炎が燃えさかることを感じたのですが、その炎は40年たった今でもますます燃えていると自分で感じています。 |
| (質問)今回の公演の聞きどころを教えてください。 |
|---|
| (回答)全部です!全部が聴きどころです。プッチーニのオペラは全部「物語」です。全てのオペラを歌っていくと、いろいろな人間を描くことになります。バルザックの「人間喜劇」のシリーズのように、プッチーニのオペラは様々な人々を描いています。特にプッチーニは女性たちによってインスピレーションを与えられていました。自分の人生に関係している女性たちをモデルに描いているものもあります。プッチーニのオペラに出てくる男性たちは、ある意味、みんなプッチーニの色々な側面なのです。愛情深かったり、優しかったり、時には酷いことをしたり、野心に満ちていたり、ロドルフォだったり、マリオだったり、カラフだったり、いろんな性格がその登場人物に現れていて、それはある意味プッチーニの人生を語っていると考えられると思います。 ですから、今回初期の作品「妖精ヴィッリ」「エドガール」からも歌うということで、彼の全てを発見できるという構成になっています。色々なアリアを歌うときに、それを全て、もちろん今の成熟した自分として歌うので、20年前や30年前とは違うのですが、60歳の今の自分が成熟したロドルフォを歌うけれど、その表現が成熟しているのであって、若い希望に満ちた詩人の彼を表現できたらと思ってますし、それは「マノン・レスコー」のデ・グリューも「外套」も「蝶々夫人」も「西部の娘」もみんな同じことが言えると思います。 これらの全てのアリアを1日で1人で歌うのは、そういう意味で大きな挑戦になるのです。プッチーニのアリアを歌うのはとても難しいですから。 そのことを日本の皆様が、その挑戦を評価してくれたらいいなと願っています。皆様のために全力を尽くしますし、それは偉大なる天才プッチーニに捧げることにもなるわけですし、私はキャリアの中でずっとプッチーニを歌ってきたので、ある意味、彼に対する義務、自分がやるべきことだと感じています。それを日本の皆さまのために歌えて嬉しいですし、それを評価して頂けたら幸いです。 少し前に、妻のアレクサンドラ・クルザクとアルバムを作りました。“Puccini in Love”という題名で、プッチーニのデュエットをすべて歌ったのですが、そのブックレットの中で、これらの二重唱をつなげていって、ひとつの物語を書いてみました。それがとてもうまくいったので、プッチーニはやはり色々な人の人生を描いて、結果として「人間」というものの生涯を描いているのだなと思いました。 |
| (質問)年齢が60を超えてベテランだと思いますが、今のご自身の声の時期は、円熟期、ピーク、それともまだこれからなのでしょうか。 |
|---|
| (回答)声は人生のように美しいものだと思います。それは肉体と同じで、写真をとると20歳の自分、30歳、40歳の頃とはまた違うのでが、それぞれが全て興味深い。 声にしても、若い頃の声は、少し遠慮を知らないというか、考えなしで歌っているというか、そういう声も、それはそれで素敵だと思うのですが、年とともに、繊細さや儚さを獲得していく、それが加わっていくということもあります。 例えば、私がエンリコ・カルーソーの声を聴いていて、1903年の彼の素晴らしい力強い声も好きなのですが、1921年に亡くなる前の1920年にはナイーブさが加わった声の音色があると思います。それはそれで非常に面白いし、私はその声も愛しています。 カルーソーは48歳で亡くなっていますが、彼が60歳まで元気だったらどういう声だったのか、成熟した声になったのか、経験を積んでどんな声になっていたのかを自分が歌いながら想像することがあります。 人生は難しいときもあれば、美しいときもある。それが自分の中にあるし、それを自分の声帯で表現していくというのが歌手なので、それは20歳から、40歳、60歳と声は違いますが、全てが興味深いと自分は受け止めています。弱さもあれば、強さもある、それが人間の声じゃないでしょうか。 |
| (質問)声に関して、キャリアで大事なのが、勉強と情熱だそうですが、具体的に声を保つためにしていることがありますでしょうか。 |
|---|
| (回答)やってることはあります。それは可能な限り明るい声で歌うようにしています。それは過去の名歌手を聞いても、長くキャリアを続けている人たちの声は、明るい声をしているんです。若い頃はもう少し暗い声を出していたときがあって、そういう暗い声、より成熟した声を出そうとすると、声が年をとってしまうことにつながるということに気が付いて、できる限り明るい声で歌うというのを続けているということは言えると思います。 |
| (質問)あらゆるレパートリーをこなすアラーニャさんですが、6月の来日公演は周年を記念したオール・プッチーニ・プログラムとなっています。アラーニャさんが考えるプッチーニの音楽の美しさ、作品の魅力、そして歌うことの難しさはどんなところですか? |
|---|
| (回答)プッチーニは天才的であると思います。世界で最も有名な、最も上演されるオペラを5つ選ぶとすると、その中の3つがプッチーニなのではないかと思います。例えば、「カルメン」、「ドン・ジョヴァンニ」「蝶々夫人」「トスカ」「ラ・ボエーム」というところではないでしょうか。もちろん「リゴレット」なども入ってきますが。 けれどもプッチーニは、最初のいくつかの中に確実に入っているものです。それはなぜかと言うと、プッチーニは非常にモダンであり、映画的な音楽であり、とても感情を表す音楽であるため、直接聴衆の心に触れるのです。それは自然な人間性を表現しています。 例えば、“神“という宗教的なものであったり、神話であったり、もしくは歴史的な人物などが登場するという物語ではなく、非常に素朴なごく普通の人々のお話です。例にとれば、「ラ・ボエーム」もそうですし、「外套」や「マノン・レスコー」もそうです。だから彼の音楽は一般の人々の心に触れるのだと思います。 |
| (質問)フランスオペラとイタリアオペラを二大レパートリーとしていますが、言葉の上ではもちろん完全なバイリンガルでいらして、ただ音楽的要素というのが全く違う、似ているようで全く違うように思われるのですけど、それぞれのレパートリーを歌われるときに、心がけていること、フランスオペラを歌う時に、イタリアオペラを歌う時に思いを抱いていること、それぞれにどのような違いがあるか、特徴があるか教えて下さい。 |
|---|
| (回答)自分はやりたいことをやってきたということがまずあります。自分がやった方がいいと感じるものを歌ってきました。若いときに、グノーの「ロミオとジュリエット」のロミオを歌いたいと言った時に、劇場の人たちからは、「君はロミオじゃないでしょ」「フランスオペラじゃないでしょ」「だって君は、イタリア系テノールだから、イタリアの声をしているから」と言われました。でも私はフランスものをやりたかったですし、歌いました。それがうまくいったので、今度は私はフランスオペラの典型的な歌手になり、世界に対してそのように認識されることになりました。 実際はレパートリーとしてはどちらも自分は愛していて、イタリア気質の感情表現、情熱をフランスのも、例えば、ウェルテルなどにも持ち込んで歌うということは私が始めたことだと思います。でもそれは、フランスのスタイルを保ちつつ、フランスのディクションを正しく保ちつつ、そこに情熱を加えていったということで、だから私以前の人たちのフランスオペラの歌い方はもう少し優しげな歌い方に終始していたと思うのですが、そこに私がイタリア的な情熱を持ち込んだと言えるかもしれません。なぜなら、自分の中には元々の自分の血という意味で、イタリアの魂を感じるからです。 因みにこの2つのフランスオペラ、イタリアオペラだけではなく、他の歌も好きで、例えば、ドイツもので、「ローエングリン」を歌っていますし、これからも歌う機会があればいいなと思っています。大好きな役です。 ところで、CDのレコーディングが最近終わったばかりなのですが、「ロベルト・アラーニャ60」というタイトルで、そこに私の熱い気質やキャリアがその中で分かるようになっています。そこには知られざるアリアをたくさん入れるようにしました。それはある種の挑戦でもあります。アドルフ・アダンの「ロンジュモーの御者」やマイヤベーアの「ユグノー教徒」などが入っていて、この中では8つの言語で歌っています。ポーランド語も入っており、それは妻に捧げる意味もあり、モニューシュコ作曲の「ハルカ」等も入っています。その他にもスペイン語、英語などでも歌っています。 このような方向性やアプローチは私のミッションだと思っていて、新しい可能性をいつも探り、私はいつも好奇心に満ちています。自分が愛するもの、自分が発見したものを多くの人に伝えていきたいといつも思っているので、だからイタリアオペラやフランスオペラもそうですが、それ以外も素敵な音楽であれば、例えば南米のもの、スペインのもの、宗教曲なども歌っていますし、それはそういう気持ちがあるからです。その可能性が私にはありましたし、自分が望んでいたよりも多くのことを自分がやることができているということを感じています。 |